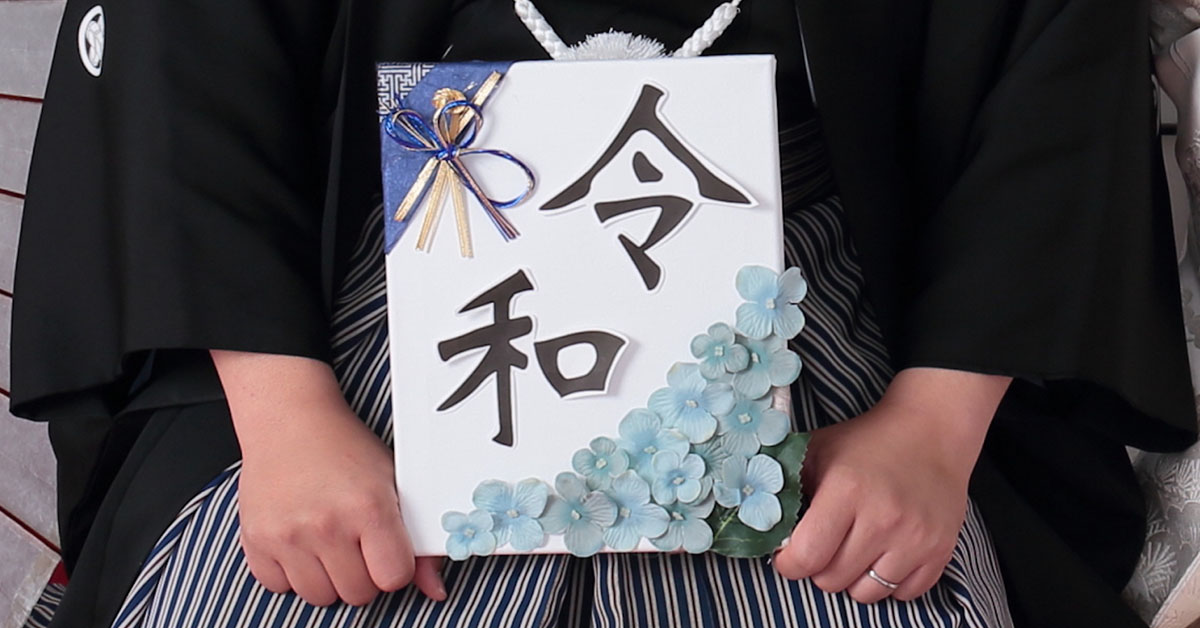新元号は令和(れいわ)!
さて、2019年4月1日、菅義偉官房長官により「平成」に続く新元号が発表されました。
その名も「令和」(れいわ)です。
皇太子さまが新天皇に即位する5月1日午前0時に施行される。
皇位継承前の新元号公表は憲政史上初めてです!
出典は万葉集の「梅花の歌三十二首」
新元号の出典は、日本最古の歌集「万葉集」の「梅花(うめのはな)の歌三十二首」からだそうです。
「初春の令月(れいげつ)にして、気淑(よ)く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披(ひら)き、蘭は珮後(はいご)の香を薫す」
安倍晋三首相は、「令和」という元号に込めた意味を「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ」と語っていました。
『万葉集』を典拠にした理由について、「1200年余り前に編纂された日本最古の歌集であるとともに、天皇や皇族、貴族だけでなく、防人や農民まで、幅広い階層の人々が詠んだ歌が収められ、我が国の豊かな国民文化と長い伝統を象徴する国書であります」と説明。
「悠久の歴史と四季折々の美しい自然。こうした日本の国柄をしっかりと次の時代に引き継いでいく」と語った。
響きが美しく、とてもいい元号だと思いました!
万葉集にはなんと鶏の歌もある
万葉集には、鳥を詠んだ歌は600首ほどあります。
鶯(うぐいす)やつばめなど季節を感じさせる鳥から、われらが鶏(にわとり)まで、いろいろな鳥の歌があります。
『万葉集』は、奈良時代につくられたわが国最古の歌集だ。大伴家持らの手で編纂されたといわれ、全20巻に約4500首の和歌が収められている。鶏の歌は14首。「とり」「かけ」「にわつどり」と呼ばれるとともに、「東」の枕詞として「鶏が鳴く」という言葉があることからも、刻を告げる鶏が当時の人々に親しまれていたことがわかる。
第七巻 庭(には)つ鳥、鶏(かけ)の垂(た)り尾(を)の乱(みだ)れ尾(を)の、長き心も思(おも)ほえぬかも
第十一巻 暁(あかとき)と、鶏(かけ)は鳴くなり、よしゑやし、ひとり寝る夜は、明けば明けぬとも
第十八巻 鶏が鳴く、東(あづま)をさして、ふさへしに、行かむと思へど、よしもさねなし
昔から鶏は愛されていたようです。
ちなみに、万葉集編纂当時の7世紀後半から8世紀後半の焼き鳥の歴史については、日本初の「食肉禁止令」が発令された時代です。
ここから鶏肉が食べられるようになるまで……何年?
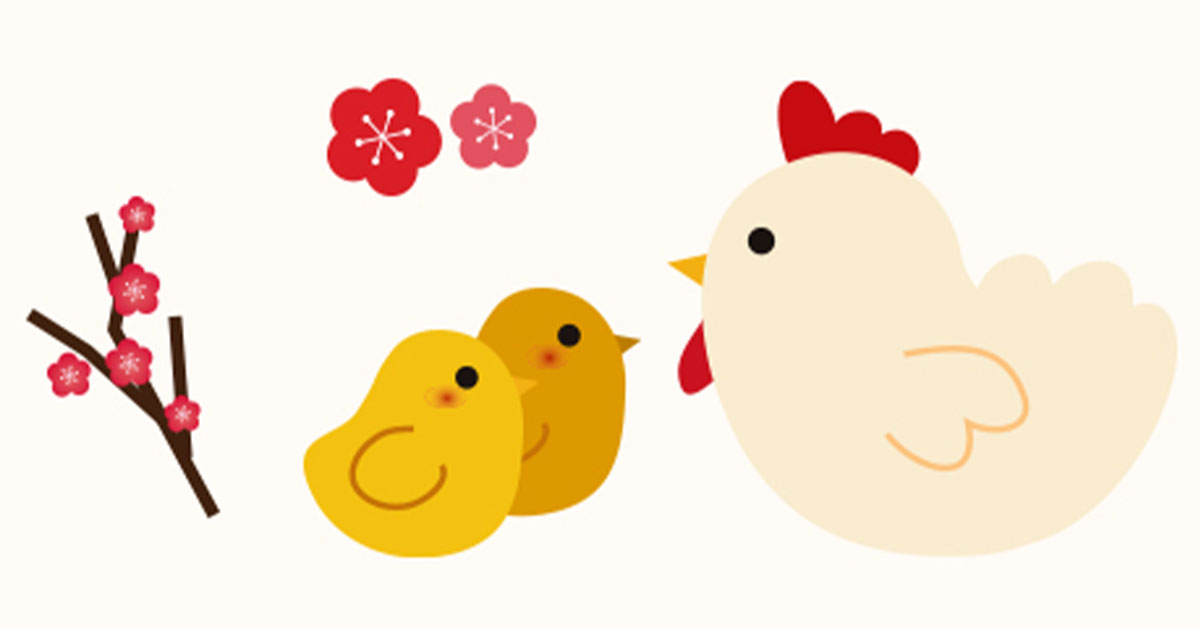
まとめ
新しい元号「令和」(れいわ)。口に出せば出すほどいい元号です。
万葉集の4500首のうち、まさか鶏の歌が14首もあるとは思わなかったので驚きました。
新元号になっても、焼き鳥の美味しさは変わらないから、もりもり食べ続けましょう。
そして、新元号「令和」(れいわ)にこめられた願い、受け取りました。
鳥取県の焼き鳥通販・大黒堂のインターネット通販サイトの販売責任者。
好きな焼き鳥の部位はねぎまです。ねぎともも肉の華麗なるコラボに勝るものなし。
パン屋の夫と小学生男子をいかにお腹いっぱいにさせるかを常に考える日々。